3 知は力なり
興味・関心が 奪われる
先生や親が、自分の解釈を正しいと思い込んで子供に押し付け、子供の内面を知ろうとしていない
これが、日本の学校の、今の常識です
そうすると、悲しいことに、子供も、他人の内面を知ろうとしなくなるんですね…
E くんも、私も、「自分が正しい、相手が悪い」と思って不満を持つだけで、相手のことを知ろうとしていないんです
従順他律の社会では、人々は不満を抱えます
そして、他人のことを知ろうとしなくなります
他人のことを知ろうとしなくなる、ということは、どういうことになっていくでしょうか…?
他人は自分を映すための鏡です
他人を知らないままになるということは…
鏡を見なくなるんだから…
自分のことが分からなくなります!!
自己理解ができなくなります
生きる方向も分からない
飛べる方法も分からない
決める方法も分からない
夢の方向も分からない
MOVE IT!MOVE IT!
目覚ませ NOW!
先生が【行動を指示する】ことによって、
『人(他人・自分)への 興味・関心を持たない子供』になっている!!
先生が【行動を指示する】ということを行っていると、「人への興味・関心」を子供がもたなくなります
別の言葉で言い換えると…
学ぼうとする心が奪われるのです
「相手のことを知りたい・知ろう」と思わなくなります
「相手が間違っている」「相手が悪い」と思うようになります
だから、自己理解ができないままになって…
「自分のことについて、思い込み・勘違いしている状態」になってしまうわけです
自分のことを知るためには、自分の歴史を知ることが必要です
自分の歴史は、家庭や学校でつくられてきました
BTS が学校三部作で表現してきたのは、「学校がおかしい!」って言っているんです
幼子を苦しめる学校は、「人間がいる場所になっていない!」ってことなんですね~

目を覚まそう!!
私は、同じようなメッセージを伝えています
「学校がおかしい!」って!!!
あたかも人間を育てているかのように振るまっている「嘘つきの学校」を、知ることが必要なんです
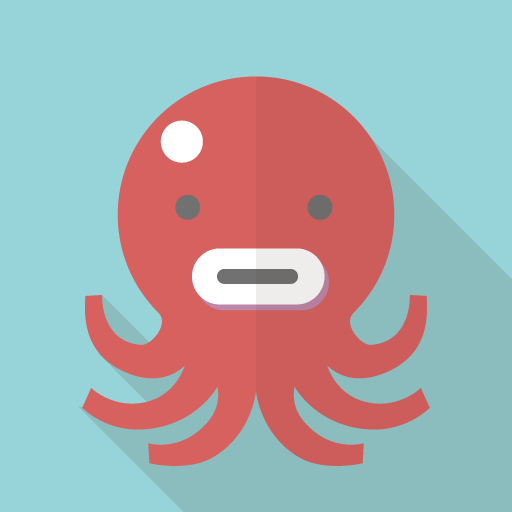
憲法、法律、学校の教育目標は「人間を育てるのが目標です」と言っているのに、実際には、「アンドロイドをつくるのが目標」になっているということですぞ~
自分たちの歴史を一緒に学ぼう!
知は力なり~♬
古い価値でできた「アンドロイド製造工場」と、新しい価値でできた「人間の学校」と比べることで、それぞれの特徴が浮かび上がります
SPEAK MYSELF
先生や親:「分かった?」
子 :「うん!」「分かってるよ~!」
話をしている人が「解釈している世界」と、聞いている人が「解釈している世界」は、別物だから、話し手の意図が聞き手に伝わっているかどうか、この方法では確認できません
お互いに、自分の解釈が正しいと思い込んでいるままになる可能性が出てきます
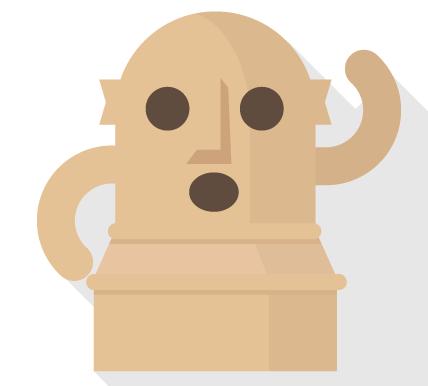
私は、我が子と不毛なやりとりをしていたのに、確認したつもりになっていたのです!
何度我が子に、驚かされたことでしょう…
話し手は、自分の宇宙と相手の宇宙が違うということを認識していません
違いを認めていないんですね
自分の宇宙は、自分にしか分からないのです
解釈によって、その人の世界が作られていきます
子供が解釈したことを子供が表現することで、話し手の意図することが伝わったかどうか、ようやく確認することができます
「〇〇ということだよね~」と子供が言葉で表現する、ということです
子供が解釈したことを言葉で表現すること(SPEAK MYSELF)によって、大人は子供の宇宙を知ることができます
「自分自身のことを話す(SPEAK MYSELF)」ということによって、お互いに違いが認められるようになります
お互いに表現し合うことによって、違いが分かるようになります
人間の学校
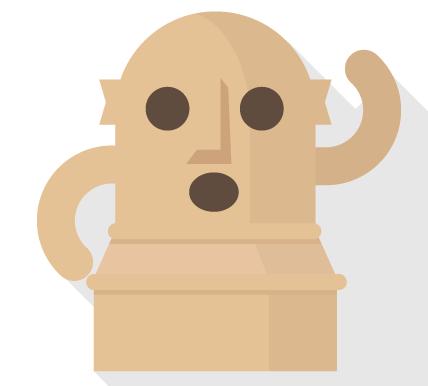
前のページ「信号がチカチカしたら止まりましょう」の話の続きです~
ファシリテーター
「1歩進んでいたら戻り、3歩進んでいたら早歩きをする」というのは、先生の解釈なのです
だから、表現する「議論の場」が必要なんです
子供が自分の内面を言葉にして表現することです
そうすることで、子供は、
自分のことが分かるようになります
他人のことを知ることができます
だから、
「違いを認め合うこと」ができるようになります
「5歩進んだ時に、信号がチカチカしたらどうするか」
「1歩進んでいた時なら、渡るか渡らないか」
「学校に遅刻しそうな時、渡る直前に信号がチカチカしたらどのようにするか」
「信号が途中でチカチカしたら、走った方が良いか、歩いた方が良いか」
などなど…
内面を表現するためのテーマを与える
これが、親や先生の役割です
先生は、ファシリテーター(意見を引き出し、話し合いをより良いゴールに導く人)です
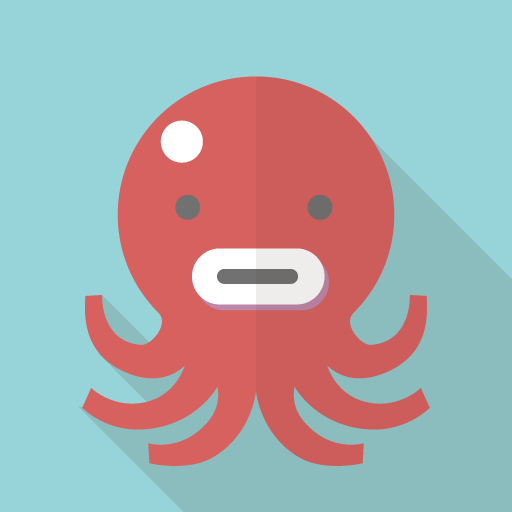
『【行動を指示する】のが先生の役割』というのが、教育発展途上国の常識…
「自分の解釈を教え込むのが先生」ってことだね~
『議論のテーマを与えるのが先生の役割』というのが、教育先進国の常識…
「ファシリテーターの役割をするのが先生」なんだね~
力のあるテーマを与えられた子供たちは…
「ああでもない、こうでもない」
「こういう場合にはこうなる」
「そういえば前に、こういうことがあった」
自分の体験談などを基に、
考えます!!表現します!!
議論することは、表現し合うこと
人間らしく、新しい脳みそを使います!!
少人数のグループで、議論を繰り返し行っていくことで、自分の宇宙が他人の宇宙と違っていることを知り、違いを認めることができ、思いやりのある子に育っていきます
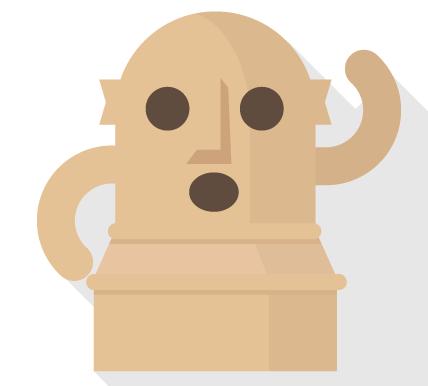
少人数にする理由は…
緊張しないから
発言の機会が多いから
自分が主人公になれるから
私のような引っ込み思案の人でも、少人数の場だと表現できる!ってことです
つまり、1人1人の小さな『声』まで、全体の場に届くんですね~
議論を通して様々な知識を得ます
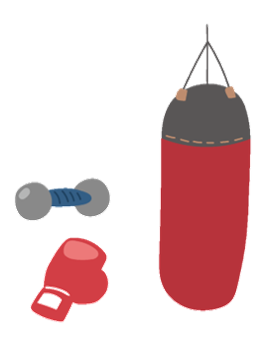
自分の内面を言葉で表現することで、自分のことが分かるようになってきます
「自分についての知識を得る」ということです
他人の内面が表現された言葉を知ることで、自分が持っていなかった知識を得ます
「他人についての知識を得る」ということです
さらに、他人の内面を表現された言葉を知ることによって、他人の内面を想像する力が身に付きます
知識を得ていくことによって、自分の宇宙がどんどん良いものになっていくから、子供は嬉しくなっちゃうんですね~!!
「もっと知りたい!」と、繋がっていきます
「もっと知りたい!」という意志が生まれてくる
これが、人(他人や自分)への興味・関心であり、学ぼうとする心です
たくさんの人々の考え方・知識の中から、話の筋が通っているもの、自分に合うものを、子供は自分で見つけます
そして、自分で選択します
そして、自分の考え方ができます
深まっていく!
さらに議論していくと、話が反れていくように感じられることもあります
でもね… 反れているのではないのです
知識が増え、深まっている のです
新しい視点が生まれます
大人が議論のテーマを与えなくても、自分たちで「そういえば、こういうことがあったんだけど、どうすれば良かったのかな?」「もしもこういうことが起きた時にどうしたらいいか知りたい」などと、信号を渡っているときの自分について、自分たちで学ぼうとします
「車が向こうからやってきたら?」
「渡っている時に忘れ物をしたことを思い出したら?」
「友達と話すのに夢中になっていて、信号に気付かなかったことがある」
「運転手さんて、どこを見ているのかな?」
こうやって、自分たちで発展させて学ぼうとしている場合が多いものです
「横断歩道を渡る前にチカチカしたら、止まる」
「一歩だけ進んでいたら、戻る」
「二歩以上進んでいる時にチカチカしたら、歩き続ける」
などなど、いろんな場面を想像して、自分たちで考えてより良い答えを見出そうとします
グループで話し合って導き出した結論を、最後に全体の場で発表させ、学びを共有すればいいわけです
日本では…
先生は、「余計なおしゃべりをやめなさい」「まずは、聞くのが基本なんだから、話を聞きましょう」って【行動を指示】して、アンドロイドにしようとします
遠足の時の横断歩道の渡り方を学ぶために、「信号がチカチカしたら止まりましょう」とだけ言っても、1人1人違う解釈をして「自分が正しい」と思い込む子供を生み出しているんですね
「横断歩道の渡り方」について、思考が深まっていません
そして、場面に応じた判断力が身に付きません
議論の場があったとしたら…
私の体験談の例に当てはめて考えてみます!
横断歩道の渡り方について、「議論の場」を事前に先生が設けていたとします
「人間」を育てようとしてくれていたら、こういうふうになっていくのではないかと考えられます
先生は…
先生は、遠足の直前に「横断歩道の渡り方は、この前、議論したよね~ 思い出そうね」と言います
議論したものを図や文字として残していたら、それを見せることで子供が思い出せますね~
判断を間違えて止まってしまった E くんには…
「どうして横断歩道の途中で止まったの?」とその行動について尋ね、表現させます
子供が正しさを見出せるように、先生と子供が「議論」することも必要になるんですね~
「最初からうまくいく」なんてこと、ないのが当たり前なんです!
学校は、間違えるところなんです
「失敗から学ぶ」「経験から学ぶ」のが、学校です
経験することで、身に染みて分かるようになります
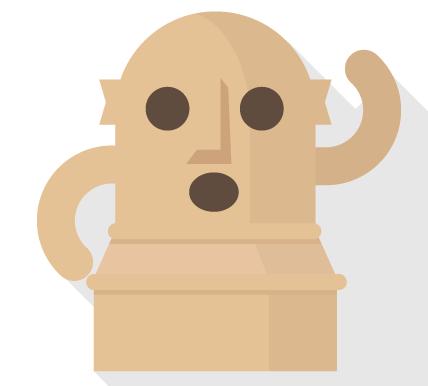
「失敗」に代わる日本語が欲しいな~なんて、いつも思っています
解釈が違っていただけなのだから!
違うことをするのが、当たり前なんだから!
いろんな経験をして心を練っていく場所が、学校なのです
日本では…
先生が子供を叱りますけど…
「自分が指導していないと思われるのが困る」からではないかと私は思っています
道徳を教え込んでいる学校で、子供が失敗をしたら責任は先生になります
先生は子供に考えさせず、指令を出しまくっているのですから…
他人軸の子供を育てているから、先生は保身が必要になっちゃいます
「責任は、工場長です!」となるから、アンドロイドのエラーはおこさない方がいいんです
あるいは、「悲しい」というのもあるのかもしれないですね
一生懸命伝えているのに、それが伝わらないから、裏切られてしまったように感じちゃう…
だから、何とか伝わって欲しくて、叱っているのかも…
学校は、子供が失敗できない場所になっているんですね
「横断歩道の途中で止まるなんて、ダメでしょ!」
先生の解釈と異なる行動、先生の決めたことに従っていない状態
こうなると、先生は注意したり叱ったりします
その子に判断力が身に付いていないのは責任が先生になるから、一生懸命、先生は子供に自分の価値を教え込みます
教育先進国では、自分の考えを持ち、表現できる子を育てようとしています
教育発展途上国では、指示に従って(ルールを守って)行動できる人を育てようとしています
実際の学校の目標が違うんですね!
日本では、教育先進国と同様の目標を掲げていますが、実際には、指令に従うルールを守らせようとしている、ということです
つまり、「学校は嘘つき」なんです
先生の価値を教え込もうとして叱っても…
子供は、自分で考えて行動できる子には、なりません!
「先生に怒られるから、こうしなきゃ(must)」と言っている子供になっていたら…
その子は「恐怖から逃れたい」というマイナスエネルギーを持ちながら行動している、ということです
「一緒に幸せになりたい」というプラスエネルギーを生み出し、実際に幸せになるシステムに変えて行っているのが、教育先進国なのです!!
一緒に幸せになろうとしているのが、教育先進国なんですね!!
E くんは…
Eくんは、「場面に応じて、自分で考えて行動すること」を議論によって学びました
学んだことが自分のものになっていたら、自分で判断して行動しようとします
もし、学んだことが自分のものになっていなくて、「横断歩道の上で止まる」という行動をしたとしても、「先生に言われただろ!!」と他人の責任(他人軸)にすることはありません
日本では…
先生が指令を出すから、その行動をしている責任は、先生になります
責任はアンドロイドを操作する側になるのは、当然なのです
アンドロイドは言われたとおりに動こうとしているだけであって、アンドロイドが指令通りに動かないというトラブル状態になったら、その責任は工場長にあります
自分の頭で考えて判断して行動するのが人間なのですから、自分の責任です(自分軸)
議論が常識になっている学校にいる子供は、「先生に言われたことを守ろうとして怒る、ということはしない」と想像できます
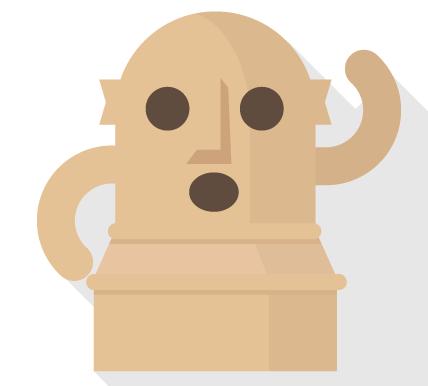
道徳を教え込まれると、その道徳を守っている「自分が正しい」となります
でも、存在しているのは解釈です
それぞれが違う解釈をしていても、それぞれが「正しい」というのは、話の筋が通っていません
「自分が正しい」と思っている、というのは、思い込みです
私は…
私は、「人によって解釈・考え方が違う」ということを議論によって学べますね!
学んだことが自分のものになっていたら、Eくんの考え方を想像しようとし、「そう解釈したんだね~」と認め、自分と異なる解釈・考え方をする他人を受け入れることができるようになります
E くんに対する「不満」は生まれません
もし学んだことが自分のものになっていなかったとして、「E くんが間違っている!」と思っていたら、それを言葉で伝えることができる子になっていればいいのです
実際、横断歩道上で止まるのは、間違っています
引っ込み思案だから直接『声』を伝えなかったとしても、先生に『声』を届けようとします
自分の真心を表現するのが常識の社会では、思ったことを言葉にして伝える癖が身に付きます
「E くんは、横断歩道の途中で信号がチカチカした時に止まったから、とても怖かったです」と伝えればいいんですね~
もちろん、先生とは信頼関係を築けていることが、最低条件ですけどね
E くんの幸せのために、『声』を届けるんです
このことをこのまま放置していたら、E くんは間違った判断をしていることになります
放置するんじゃなくて、「一緒に幸せになりたい」という意志が生まれ、その『意志』と『行動』を一致させることが大事なのです!
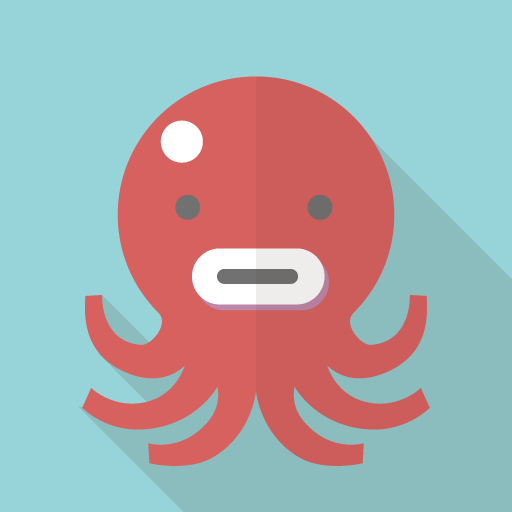
『心』と『行動』が一致しているのが、自由ということだったね~
E くんは横断歩道の渡り方について間違った判断をしているから、私の『真心』を届けることが、E くんの幸せにつながるんです
人のことを大事に思って、『声』を届けようと実際に行動すること
真心を伝えることが、誰かの幸せになります
『真心』と『行動』を一致させること、それが、自由です!
日本では…
日本の学校は、「他人への興味・関心が奪われる社会」です
「他人が幸せになる真心」を、隠すようになっています
「真心の声」を届けない子を育てているんですね
「一緒に幸せになろう」という意志が生まれたとしても…
我慢を道徳で教え込まれていると、人々を幸せにする『真心』を届けようとしなくなります
真心を伝えると、「わがままですよ~」って大人が言うんですね
「僕が使っているんだ」と真心を伝えていた S くんは、わがままだと多くの人が思ってしまいます
「怒るという表現方法が未熟だった」ということであって、真心を伝えることは、人々の幸せのために必要なことです
Sくんは、「我慢ができないわがままな子」ではありません
『真心』を伝えて、幸せになろうとしている子です
自分のことを大事に、他人のことを大事にできる子です
自由とわがままの違いが分からない人々が、自由をわがままと勘違いしている、ということです
わがままとは、他人の迷惑になることです!!
「他人のことはどうでもいい」と他人への興味・関心がない状態だと…
やはり、『声』を届けようとしません
日本の場合には、先生に『声』を届けると、「チクったでしょ!」となることがあります
だって、「失敗をしたら、先生は叱る」から!!
叱られないようにするためには、チクらないほうがいい、と思っちゃいます
あるいは、「あの子は、間違ったことをするから、先生に叱られてざまあみろ」みたいに思う子もいます
悲しい…
本当は、この真心は「幸せになるための真心」なのに、歪んだ世界では、「故障したアンドロイドが叱責を受けるための真心」みたいになっちゃいます
「一緒に幸せにになろう」と真心を届けたら…
心と行動を一致させたら…
私たちは、一緒に幸せになれるんです!!
我が子Bは、議論が常識の学校の子供のような考え方になっています
私が自由の大切さに気付けたこともあるし、自由を尊重する保育園に通ったからかも…
「一緒に幸せになりたい」という意志が生まれて、『真心の声』を届けようとする子になっている、ということです
「心」と「行動」を一致させようと、実際に行動する子です
つまり、『自分で自分の自由を手に入れようとしている子』です
アンドロイド製造工場でよく褒められる我が子Aは…
幼少期に私が指令を出しまくって、指令に従っている状態を褒めて育てた子なんですね…
「一緒に幸せになりたい」という意志が生まれても、我慢したり、そういうものかな~と思って放置してしまったりする子になっている、ということです
「心」と「行動」を一致させようと、実際に行動しない子です
つまり、『自分で自分の自由を手に入れしようとしない子』です
『真心の声』を届けようとしない人の中には、他人への興味・関心を持たない人もいるから、「一緒に幸せになりたい」という意志が生まれない場合もあります
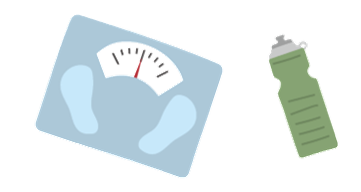
学ぶ権利
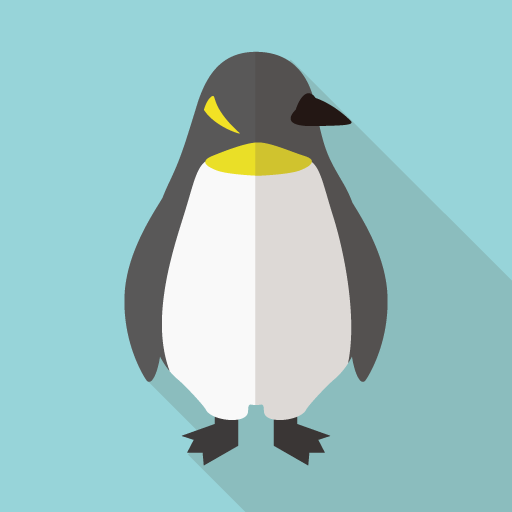
子供に議論させると、途中でゲームの話とか関係ない話をする子がいるんじゃないの~?
こうならないようにするために、「先生が決めた目標」を子供に押し付けるんじゃなくて、「子供自身が決めた目標」を持たせて取り組ませることも必要なんですね~
議論にならずに遊んでしまうような子に対しては、「この時間に何をしたいのか、どうなりたいのか」先生は子供に自分のことについて考えさせることが必要になります
子供が言葉にして表現することによって、子供は自分のことが分かるようになるんです
「自分の行為が、他人の学習権を侵害している」ということに気付かせればいいんですね
「価値を押し付けて叱るのが先生」ではなく、「ファシリテーターが先生」なのです
子供に学習の意味について気付かせることが必要になります
自由は、自分勝手・わがままとは違います
相性
自分と相性が良いと感じる先生、相性が悪いと感じる先生…
いろいろな感じ方をして、当たり前です!
どんなことを思っても、心は、自由です!
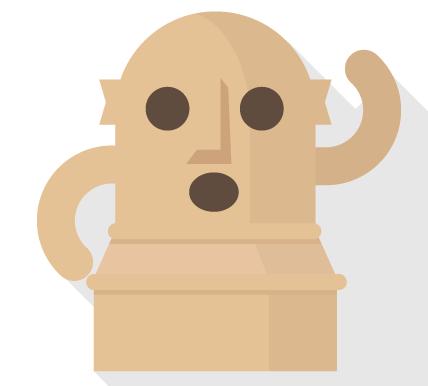
思ったからと言って、何でもかんでも表現していい、というわけではありません
内心の自由には制限がありませんが、表現の自由には制限があります
他人を傷つけるものは、表現してはいけないのです(表現の自由)
先日、テレビを観ていたら、不登校になったの理由の第一位は「先生との相性が悪い」とのことでした
今のシステムの中で、担任の先生と相性が悪いと感じたら…
先生も子供も、毎日が苦痛です…
今のシステムでは、不登校が増えていく一方であるのも、私は納得してしまうのです
だから…
仕事量的にも、子供の安定のためにも、たくさんの先生が必要なんですよ~!!
表現したい
「表現したい」と思っているのが、人間の自然な姿
これが、「人間とは何か」を探求し続けている人間がたどりついた、新しい考え方です
「自分たちが幸せになる社会を、自分たちの手で創造する」
それが、自由な人間の行いです
本来、人間は「表現したい」という欲求がある生き物であるから、「喋りたい」生き物なのです
意志を創造し、表現するのが、人間です
でも自分が喋るためには、聞き手の役割もいるということを身に染みて分かることが必要です
喋ることをしたければ、その相手である聞き手の役割ができるようになることも大事!!
でも、まず、喋りたいのが人間です
伝えて嬉しい!聞いてもらって嬉しい!
嬉しいから、次は、私があなたの話を聞くよ!
というように、自分が表現者になる喜びをまず先に味わうことで、他人の話を聞ける人に育っていくのだそうです
自分の話を相手に聞いてもらったら、嬉しい!
相手の話を自分が聞くことで、相手は喜んでくれる!
お互いに嬉しいね~!!
プラスエネルギーが生まれてきます
福沢諭吉の言っている「人間交際」が生きるエネルギーになるんです
日本では…
子供に表現させていません
表現させてもらえないから、我慢が蓄積されていき、子供は苦しんでいます
「表現したい」というエネルギーを出させるために、子供に合っているのが議論なんですね~!
幼いうちから議論を習慣にしているのが、教育先進国で行っていることです
話を聞く子を育てたいから、まず、表現する喜びを味わわせる
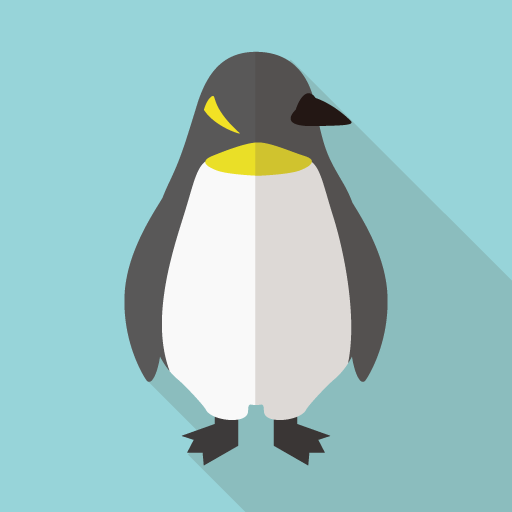
でもさ~
子供が表現しても、周りの子が話を静かに聞けなかったら困るんじゃないの~?
子供に話を聞く姿勢を身に付けさせるためには、「表現したい」というエネルギーをコントロールできるようにさせることなんですね
違う形でエネルギーを発散させることで、誰かが話している間は「静かにする」という癖を付けさせる
聞くというのにもいろんな段階があります
まずは、声や音を出さないでその場にいられること!
そうやって、大人がねらいを決めて、子供にもその意味を伝え、子供自身にも自分の目標を持たせながら、子供を育てていけば良いのです
「今は、人形を抱えながら、静かに座っていられるかな?自分が話す順番でない時には、声や音を出さないように一緒に頑張ろう」と子供に伝えていくんですね
「喋りたい」というエネルギーを、ふわふわの人形を触るというエネルギーに変換して発散させ、表現の形を変えるんです
ぬいぐるみなら、手を動かしていても、音がしません
「喋りたい」というのを我慢させるんじゃなくて、「喋りたい」というエネルギーを人形を触るということに変換して発散させ、「喋りたい」という欲求を子供が自分でコントロールできるようになればいいんです
「話し合いをする場所では、それぞれが勝手に喋り出したり、音を出したりしていたら、伝え合う喜びが失われてしまうんだよ~」
「喋っている人だけじゃなくて、聞いている人も大事なんだよ~」
って伝えていくことですね!
日本では…
「手に物を持って話を聞いていたらダメですよ」「手を動かしていたら話は頭に入らないでしょ」って先生は言います
子供は、喋りたいという自分のエネルギーをコントロールする方法が分からなくなります
「我慢させる」という方法しか、日本の先生は知らないんですね
教育の学びが必要、ということです
エネルギーを抑えつけられると…
ストレスを抱え、先生が話しているのにおしゃべりしちゃう…という子になってしまうんです
「喋りたいのが人間であって、自分のコントロールの仕方が分からないから喋ってしまう」という子供のことを、多くの先生は知らないんですね
「私が喋っているのに、静かに聞く姿勢が身に付いていない!!他人に迷惑がかかるということが、あの子はまだ分かっていない」
と思っているのが、学校の先生、ということです
「自分は正しい、悪いのは子供!」と思っているんですね
「自分は正しい」と思っているというのは、学ぼうとする心が無い状態です
先生は、他人への興味・関心を持たない大人になっているから、子供のことを知ろうとしていない、ということです
教育の学びが必要、ということです
あと…
先生は忙しすぎるから、考える余裕、学ぶ余裕がないんです!
「人間とは何か」を探求し、学び続けている教育先進国は、子供の『心』を知ろうとしています
学ぼうとする心(他人への興味・関心)があるから、子供のことを知ろうとしているんです
だから、「表現したい」と思っているのが人間の自然な姿だ、ということを導き出しています
「話を聞いてもらって嬉しい! → だから、自分も静かに話を聞こう!」って思える場面をたくさん作ることによって、話を聞こうとする子供を育てています
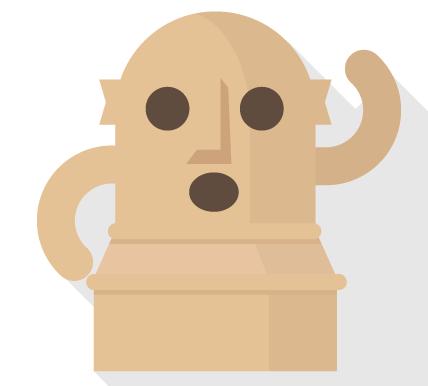
自分の真心と行動が異なる状態を我慢と言います
静かにしていることを「我慢」と本人が思っていなければ、我慢になりません
成長していくにつれ、だんだんと、話の内容を解釈することに目標を移行していけば良い、ということです
人形を触っていなくても静かに話を聞けるようになる時は、そのうちやってきます
議論の場所を設けることで、知識は増えていきます!!(^^♪
学校とは…
話したり聞いたりして表現し合い、相手のことを知り、自分のことが分かるようになり、「人間交際」の喜びを感じる場所
日本では…
今の日本の学校は、どんな場所でしたっけ…?
学校とは…
【行動を指示】され、その通りに動き、人への興味関心が奪われ、自分のことが分からなくなり、「人間交際」の喜びを奪われる場所
人間が壊されていくんです
だって、学校は、アンドロイドにしようとする場所だから!!
子供は「表現すること」を我慢させられているから、学校が苦痛になります
「〇〇しましょう」という指令に従って動こうとする場所が、日本の学校です
先生の価値を刷り込まれ、黙って指令に従い、意志を表さずにおとなしくしている子が、いい子なのです
「誰かが話している時に静かにする」というのは、合っています
でも、「静かにしましょう」と、行動を指示する「伝え方」は、間違っています
行動を指示している先生は、アンドロイドです
行動を指示されていて、何も考えずに指令の通りに動いていたら、子供はアンドロイドになります
大人自身も、子供の『心』を想像する
想像するのが、新しい脳みそを使う人間です
「自分が喋っているときに誰かに聞いてもらえると嬉しい」という喜びをまず味わわせることが、まず最初のステップなんですね
聞くことではなく、表現することが先です!!
話の内容を解釈しながら聞いているかどうか、ということは、もっと先のステップです
その子によって、その時間の目標というのは異なります
だんだんと、話の内容に耳を傾けることができるように育っていきます
刷り込みは不自然で、自分が壊されていくからアンドロイドになるけど、
教育は自然で、自分が自分らしくいられるから人間になります
芸術
「表現したい」という思いを誠実にコントロールし、芸術を発展させるのが人間です
芸術を発展させるエネルギー源は、「人間交際の喜びを味わいたい」という意志です
だから、私たちが表現する意志(言葉)は、芸術なんですよ~!!
「誰かとつながっていたい」「誰かと一緒に幸せになりたい」と思っているから、私たちはSNSで交流したり、言葉にして『真心』を伝えているんです
「表現したい」と思っているのが、人間です

「表現したい」と思って表現し、誰かとつながろうとしているのですから、これが、「芸術」です
自分の表現によって、誰かの心を動かしているから、芸術です
つまり、人が表現しているものは、全て芸術 ということです
全ての叫びは、芸術!!(♪Beautiful Beautiful)
意志(真心)を表現したいと思って、表現するのが人間です!!
音楽やダンスによって、芸術を「誠実かつ巧みに表現しているアーティストたち」は…
人間らしい人間
ということができるんですね~!
他の宇宙が想像できない
でもね、「考える」ということが苦手な子供もいます
他人の宇宙を「想像する」ことが苦手な子供もいます
生まれつき、自分の宇宙だけが全てになってしまい、他にも宇宙があることを理解できない子もいます(自閉)
そういう子には、細かく教え込んであげます
「渡る前にチカチカしたら止まります」
「1歩進んだときにチカチカしたら戻ります」
「2歩進んだときにチカチカしたら戻ります」
「3歩以上進んだときにチカチカしたら進みます」
「チカチカしても、歩き続けます」と教え込むことが必要な子もいます!!
幼いうちに、その子の特性に周りの大人が気付いてあげて、優しく教え込んであげればいいのです
それが、その子が幸せに生きるために必要な学びだからです
日本では…
「他人の宇宙があるということが、生まれつき認識できない子が存在する」ということを、このブログを読んでいただいている方は、知っているでしょうか?
だから、インクルーシブという考え方が必要なんですね
日本だと、障害のある子供は学校や教室を分けられちゃうけど、教育先進国だと一緒の学校・教室にいます
いろんな人がいるのが社会なのであって、その子と一緒に社会を作っていくことなのだから、学校の環境も多様性の認め合える社会にすることが、本当は必要なのです
人によって成長のスピードがそれぞれ違うのに、日本では、生まれ年できれいに区切って学年を分けています
これも、とても不自然な状態だと私は考えています
教育先進国だと、1つの教室の中にいる子供の年齢も、多様です
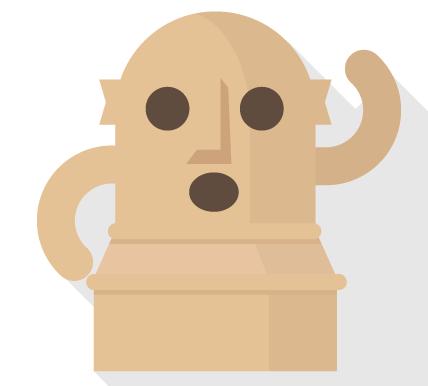
日本は、障害の有無によって学校や教室を分けていることを国連から問題視され、2022年に指摘を受けているようです…
私が「間違ってるよな~」と思っていることを、国連が指摘してくれていたんですね~
指摘されていたこと、さっきまで知りませんでした~
多様なのが、当たり前なんですね~
いろいろな考え方、いろいろな困り感を抱えている人がいるのが当たり前なのだから、互いに理解し合おうとする姿勢を育てているんですね
家庭環境
「宇宙を自分で作っちゃだめよ!あなたの宇宙は私が作るの!」って親に言われている子もいます
そういう子には、「宇宙を自分で自由につくっていいんだよ」って安心できる環境をつくってあげる
宇宙に侵入して、価値を押し付ける龍を追い出すのが、周りの大人の力なんです
古い価値を信じている親に、学びの機会を与えることですね~
「あなたの宇宙なんて興味ないよ~ 勝手にしてれば~」って親に放っておかれている子もいます
親に関心を持たれないままだから、その子も他人に関心を持たず、自分勝手になっちゃうのです
無関心な親を教育するのも周りの社会の役割です
「あなたのつくる宇宙も素敵だよ~」って認めてあげて、自分勝手になってしまった表現方法を一緒に修正していくのも学校や社会の役割です
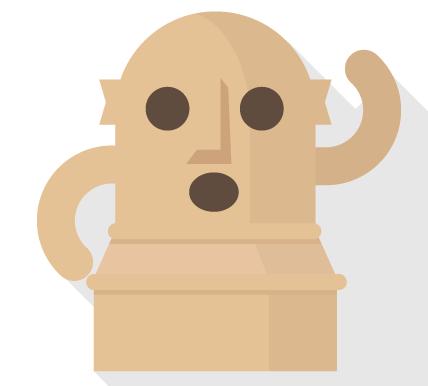
私、「教育先進国の教育に詳しい人」と思われていないですかね…
話の聞き方とか、具体的に書いていると思っているんですけど…
前に書いたオランダの教育についてのことや、ここに書いてあることのほとんどは、友人から聞いた話を基に自分の考えを入れて文章にしただけであって…
教育先進国の学校の知識がある友人の話を聞いて感動したから、それを伝えているだけなのです
話の筋が通っている感動的な新しい世界の話だから、記憶力の低い私でも、覚えていられるんです~
本も読んでないし、講演も聞いたことないし…
テレビで見て「素敵だな~!」と思ったことはあるけど…
新しい脳みそを使って幸せになる、というのは、
古いシステムに子供をはめ込もうとすることではありません
そこにいる人々に合った「システムを創造すること」なのです
つまり、今のシステムを破壊して、新しいシステムを創造すること
人々が幸せを感じることができるシステムを創造する
それが、芸術です
知識を得て「こうなりたい(want)」という意志が生まれ、実際に行動するのが、人間なんです
まだまだ、伝えきれていないような気がしていて…
私の下書きフォルダは、文章でパンパンになっています
ボツ文章がいっぱいあるんです…
でも、これは、まあまあ気に入っている文章なので、ここに隠しておきます
あまりにも文章量が多すぎちゃって、読むのも疲れると思うので…(笑)
興味が生まれたら、読んでもらえると嬉しいです
↓
道徳や宗教の【教え】に「親を大切にしましょう」というのがあります
自分が「そうだよな~ 親には感謝してるから大切にしたい」と思っていたら、道徳の教えと自分の『心』が一致しているし、実際に大切にする『行動(表現)』をすればいいわけです
『心』と『行動(表現)』が一致しているから、幸せです
だから、道徳を信じている状態でも、真心と同じであるのだから、自分軸です
ところが、ですね…
今の日本社会は、そんな素敵な親子関係ばかりではないのです
虐待されている子
育児放棄されている子
捨てられた子
暴力を振るわれている子
ご飯を作ってもらえない子
激しい夫婦喧嘩を目の前でされる子
「あんたなんか産まなければ良かった」と言われる子
親の支配が苦しくてたまらない子
愛を知らずに育ったために犯罪に手を染めてしまう子
こんな子供たちが、
「親を大切にしたい」と思うでしょうか?
「感謝を伝えたい」と思うでしょうか?
自分の勉強時間、遊ぶ時間を削っているヤングケアラーの子は、社会から自分たち親子が大事にされていないのに、「もっと頑張れ!」と言われているように感じないでしょうか
「親を大切にしたいから助けて欲しい!」という心の叫びは届いているでしょうか
そんな子供たちにまで、感謝を強要しているのが、今の道徳です
「親を大切にしたい(want)」ではなく、「親を大切にしなければならない(must)」と、先生は子供の『心』を操作しようとするんです
子供のことを、他人に操作されるアンドロイドにしようとするんですね
素直な『心』でいられなくなるから、子供は苦しみます
『真心』と『行動』が一致しなくなります
「親に暴力を振るわれて苦しんでいるのに~!!誰も自分のことを分かってくれない!!感謝しろって言われても、無理だ~!!」と、なってしまうわけです
当然、幸福度は下がりますね
ありのままでいいんだよ
君は君でいいんだよ
君の心で思った通り、自然体でいいんだよ
真心を伝えていいんだよ
苦しいって言っていいんだよ
こうやって、子供たちを受け入れる優しい言葉をかけてもらえたら…
実際に支援してもらえたら…
人の温かさや優しさを感じることができるでしょうに…
日本の学校、日本の社会は、こういう言葉をかけてくれているでしょうか
「親を大切にしましょう」と先生が言うことによって、苦しんでいる子供がいるということ
気付いていましたでしょうか?
共通の価値、画一的な思想である「親は大切にするもの」ということを教え込まれて、考えないようにさせられてしまうと、人の心を想像できなくなります
「人の心が想像できなくなる」というのは、言い換えると「思いやりがなくなる」ということです
思いやりの心がなくなると、家庭環境に苦しんでいる子を見て、「ああ、自分があの家に生まれなくて良かった~」と思うようになります
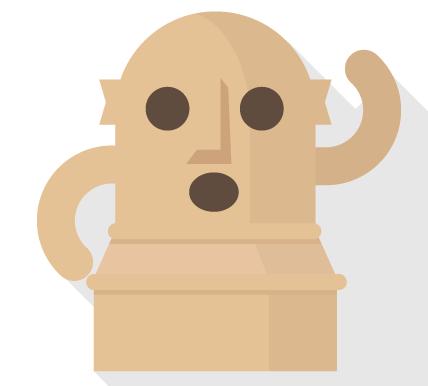
↑ ドキーッ!!とする方が多いのではないでしょうか…
何を隠そう、私がそう思っていたのです!!
これは、他人の不幸が自分の幸せになるという、異様な状態ですよね~
思いやりの心が育っていないことが、自己中心的な日本社会を生み出す要因になります
「自分さえ良ければよい」「自分がPTAのくじ引きで役員くじをひかなくて良かった~」という自己中心的な日本社会になっていくんですね
苦しんでいる人がいるのに、その人の心や生活を想像せず、苦しんでいる人のことを考えようともしなくなります
他人のことを知ろうとしないから、自分のことが分からなくなります
自己中心的だから、苦しんでいる人のことを想像しようとせず、システムについて目を向けなくなります
環境問題や紛争などの社会問題に関心が薄いのが日本人の特徴とも言えますが、これも、自己中心的と言えます
他人の不幸の上に自分の幸せが成り立っていても、心が痛まなくなるんですね
私が厳しいことを言っているように感じるかもしれませんが、臭いものに蓋をしているから、知ろうとしないから、自分のことが分からなくなります
自分たち日本人のことを客観視して、「日本の常識」が「教育先進国の常識」と異なっていることに気付くことが大切なんですね
まずは、自分たち、日本人のことを FACE MYSELF することが大事です
教育先進国の人々が「日本人は精神年齢が低い」と言っているのは、「自己中心的な考え方をしている」ということを言っているのだと私は考えています
「思いやりの心が育っていない」ということです
でも、ですね…
エンパシーは、学ぶことによって身に付きます!!
思いやりは、学ぶことで身に付きます!!
これが… 私の希望です
「親の支配から逃れたい(want)」と思う『真心』を大事にするのが、個人の自由です
この『真心』に気付いてあげるのが、学校や社会の役割です
その子の『真心』を大事にすることが、LOVE
議論をすると、学ぶと、いろいろな『心』があることに気付いて、人の『真心』を想像する力が身に付きます
「人の心を想像する」というのは、言い換えると「思いやり」です
どちらが、変?
ここまで読んでいただいた方は…
ある程度、新しい知識を得ることができたと思います
新しい知識は「自分の歴史」という知識です
今まで当たり前だと思っていた「自分の歴史を作った学校」が、「おかしいでしょ!」「嘘つきじゃん!」に変わった人がいてくれたら、私は嬉しいんです
私は一緒に幸せになりたい と思っているから、ブログで表現しているんですよ~(^^♪
たくさんの人に新しい知識を得てもらって、「子供たちを守りたい、大事にしたい、一緒に幸せになりたい」と思って『声』を届けてくれたらもっと嬉しいな~なんて思っているから、詳しく書きました
「今の学校のシステムを変えたい!それが、未来の私たちの幸せにつながるんです!」って多くの人が『声』にしてシステムを作る人に訴えることが、私たちが幸せになる方法なんです
私…
『声』を届けているんです
個人面談の時に、我が子の苦しみを訴えていますよ~
我が子だけじゃなくて、他にも苦しんでいる子がたくさんいるということを知っているから(我が子からの「子供同士の本音トーク」情報ですけど…)学校の子供たちみんなの幸せを願って、伝えています
『声』にすることで、「先生に気付いてもらいたい」と思って、伝えています
たぶん、「うるさい親だな~」「何をこの人は言っているんだ?」と先生に思われていると想像はしています
結局、担任の先生は、このめんどくさい親をあしらうために、「分かりました!そういうご意見があることを受け止めて、共有したいと思います」とだけ言って、ほとんどの場合、何もしないんです
一般企業だったら、お客様の声が届くと、何らかの反応があったり、お返事があったりすると思います
「お客様の声が、人々の幸せにつながる」という思いでいるから、小さな声にも耳を傾け、議論して改善する方法を探ることをします
商品開発をしたり、サービスにつなげたりするのが、優良な一般企業です
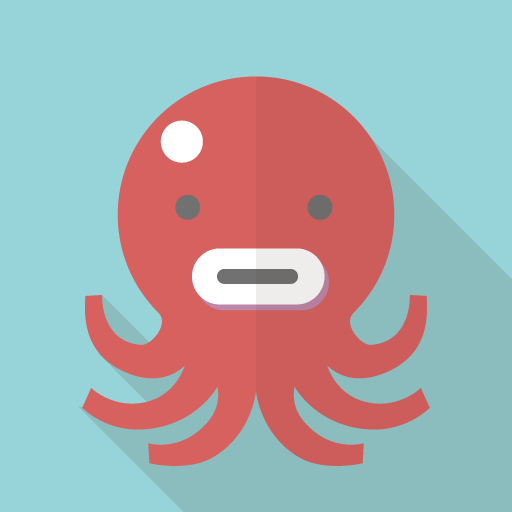
『真心の声』は、人々の幸せにつながるものですぞ~
お客さんの幸せが、社員(企業)の幸せにつながる
社員(企業)の幸せが、お客さんの幸せにつながる
というプラスエネルギーを生かしています
ここには、支配はありません
新しい価値が浸透しています
学校は、保護者の声を、放置します
制服を着ることで、「苦しくて勉強ができない」って訴えているのに、「我慢」が当たり前なのです
「保護者の声が、子供の幸せにつながる」なんて、思っていません
相手にするのが、面倒なんです
忙しいし、先生は「自分が正しい」のだから!
先生は、「自分だって我慢したし、他の子も我慢しているんだから、これが当たり前でしょ」と思っているのだと想像しています
ほとんどの場合、「制服の意味」なんて、何も考えていないのです
学習に集中して取り組めないと感じる制服を、毎日着させる意味は何?ってことです
たった1人の小さな声だから放置され、「どうしたらより良い方向に向かうか議論しましょう」なんて、考えようともしないんです
ここには、支配があるんです
「自分が正しい」と!!
結局、私1人が声にしても、伝わらないし、何も変わらないんです
塊になって、大きくなることで、伝わるし、変えることができるんです
でも…
私のまわりには、「制服を着させて、子供を苦しめていることがおかしい」って思う人がいないんです
だから、塊になりようがないんですね
塊になって伝えたくても、私の周りの人々が知識を得てくれないと、今の状態が異常であるということに気付けないんです
従順他律の常識を信じている人が、今の日本では、圧倒的多数派なのです
知識を得てもらうことで、ようやく「なんだ、今までのシステム、おかしいじゃん!」って目を覚ましてもらえるんです
つまりね…
ここまで読んでいただいている、ということは~ (^^)/
信じるのは、学校で教え込まれた「道徳」ではない!
学校が嘘つきだったんだ!!
信じるのは、自分自身だ!
個人の価値を大事にすることが、人々が幸せになれる方法なんだ!
と、知識を得ましたよね(^^)/
いつか君は叫ぶだろう、「すべては間違っていた!」
ニーチェ
ニーチェって、予言者なんです
「時代をかなり先取りした考え方をしていた」と言われています
集団の価値ではなく、個人の価値に従うことが、幸せになる方法だって伝えてくれています
今、君は、叫んでいませんか?
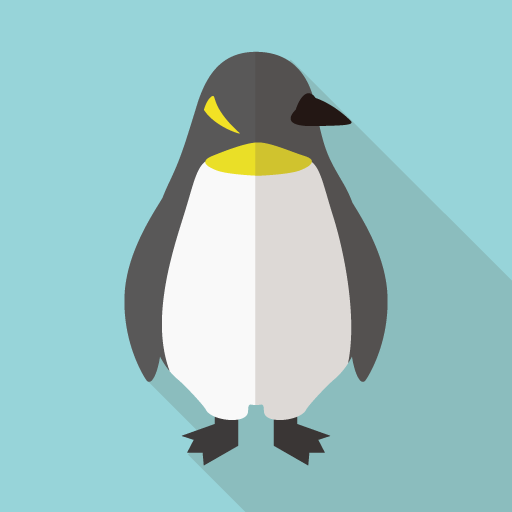
「ルールを守っていたなんて… 間違っていた!」
地動説を唱えた人は、「変人」と呼ばれました
ニーチェは、「変人」と呼ばれました
そこにある常識をおかしい!と言っている人が変なのか
そこにある常識を信じている人が変なのか
どちらが、変ですか?
ルールを守るのがおかしい!と言っている人が変なのか
黙ってルールを守っている人が変なのか
どちらが、変ですか?
そもそも、
「普通」って、何?
ステレオの道
知識が無かった時には、モノラルの道だけ見えていた
知識を得ることによって、ステレオの道が見えてくる
知識を得ること、学ぶことによって、ステレオの道という選択肢ができます
つまり、知識を得ることによって、進む道を自分で選択できるようになります
ステレオ から モノへ
分かれ道はそう 続くだろう
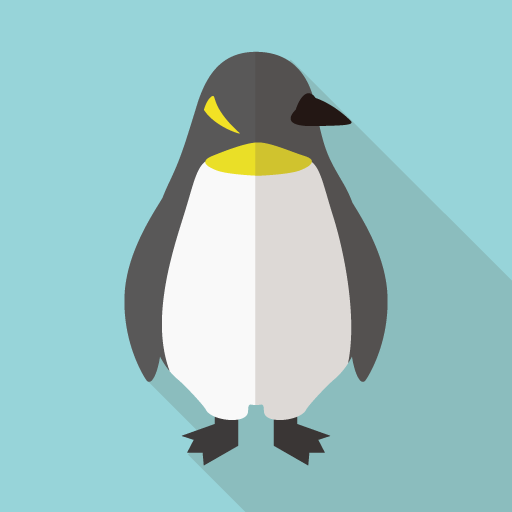
あれ~?
BTS は、ステレオの道を進んでいたのに、ステレオの道に進めない!!
なぜ、モノラルの方へ進むの~?
ペンギンさんの疑問は…
私のブログを読んでいただいていたら、もう、解釈できると思います~(^^♪
BTS は、自分で道を選択できない社会にいる、ということです
多くの人は、ステレオの道(新しい価値)を知らずに通り過ぎちゃうから、モノラルの道(古い価値)に進んでいても、痛みを感じにくいようにされています
知識があると、心が痛みます
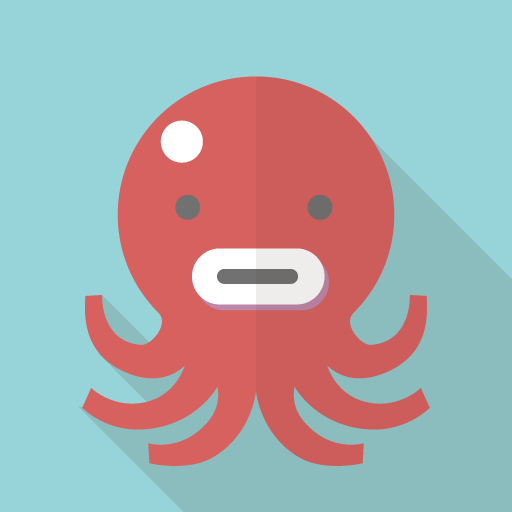
学ぶことを学校でさせてもらっていない、ということだね~
多くの日本や韓国の先生が行っている
【行動を指示する】こと
解釈の異なる子供を叱責すること
こういうものに違和感を持てなければ…
モノラルの道を進み続けている、ということですぞ~
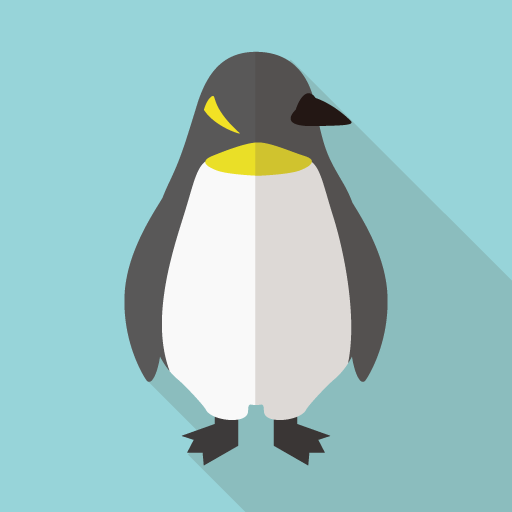
「信号がチカチカしたら、止まりましょう」と言っていた先生の「伝え方」は古いのに、違和感を自分が持たなかったということは…
古い価値を信じている、という状態になるってことか~
新しい価値を人間に創造されてしまうと、支配者の保持したいアンドロイドの常識が保持できなくなるから、学ぼうとする心を支配者は奪う、ということです
アンドロイドは、新しいものを創造されたくないんです
アンドロイドは、古い価値を守っている自分が正しいと思っています
古い価値を守っている状態を褒められて育つと、自分が正しいと思っちゃうんです
古いものを「善」だと信じて守ろうとする人々にとって、新しいものは「悪」に見えるから、アンドロイドは、人への興味関心を奪っておくのです!!
学ばないようにさせておくんですね
自由な世界で、創造するのが、人間です
だけど、繊細な感覚を持つ芸術家と言うのは…
知識を得て深く考えているから…
人のことを心から大事に思っているから…
学び続けているから…
キラキラ輝く新しい価値の世界が見えるんです!!
花様年華!FACE MYSELF!LOVE MYSELF!SPEAK MYSELF!が常識の、愛のある新しい世界です!!
社会的偏見と抑圧によって、ステレオの道は、塞がれています
モノラルの道は、死の道です
Black Swan です
踊ることを止めることは、死を意味するんです
自由を奪われ、創造することを止めさせられ、人間じゃなくなるんだから!
平和や愛を表現している人々は「個人が犠牲になり続ける常識がおかしい!」と強く感じているんですね
人間らしく考えている人ほど、自分の意志と異なる行動をすることに苦痛を強く感じます
大事にしたいと思っているのは、人々の『心・意志』だからです
意志に反して、奴隷的労働をする集団生活を異常だと思っているから、苦しみは増します
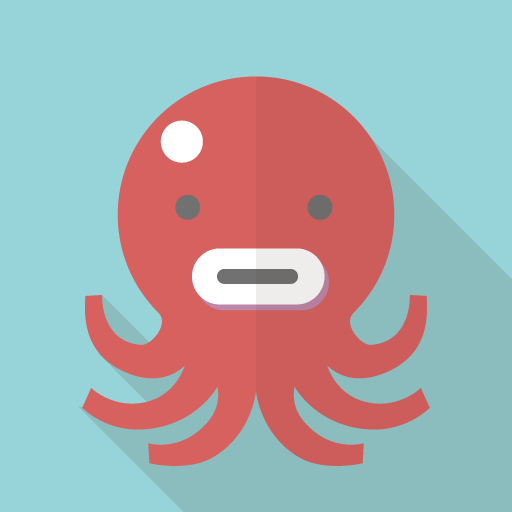
アンドロイドは、偽物ルールの道徳を信じ込まされて、意志することを「悪」「わがまま」と思わされているのですぞ~
苦痛を我慢するようにインプットされているということですぞ~
RATHER BE DEAD THAN COOL(情熱のない人生なら、死んだ方がマシ)
ジョングクの右腕で表現している言葉です
これは… LOVE MYSELF の言葉ですね!
アイドルは
知識があるからこそ、
深く考えているからこそ、
繊細な感覚を持ち合わせているからこそ、
人間のことを大事に思っているからこそ、
ステレオの道を塞がれることによって、苦痛はさらに増すのです!!!
死です!!
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES(チャンスを逃さずに行動しよう)
チャンスを逃がさずに行動しているのが、主人公です
BTS は、人を愛するエネルギーを表現し、「ARMYになら、新しい価値が伝わる!」と信じて伝え続けてきたのですから!!
BTS は、「新しい価値」をファンにたくさん伝えてきているんだから、もう、伝わるはずです!!
知識を得て目を覚ました ARMY がいるはずです
「ファンが『愛するということ』を表現できる!」って信じているのが、アイドルです
BTS のステレオの道を塞いでいる社会的偏見と抑圧を撃ち抜くことができるのは…
えっと…
名前がみつかったかな~?
誰か、撃ち抜こうとする人間はいませんか~?
相変わらず、意志を表す人間が、いないんです
「自分が戦っている」と思い込んでいる人が、多すぎます…
多くの人は、アンドロイドとして生きる道を自分で選択しています
ARMY は…
私以外、誰も銃を構えていないんです
兵士は私1人だけだから、撃ち抜けないんです~
ARMY の名前を持っているのは、私だけ ってことです!
名前の意味通りに、自分が意志を表して実際に戦うことで、名前があるARMYになれます
名前のある主人公になれるのは、実際に、意志を表して戦う人です
新しい価値を、MC となって発信する
これが、ARMY なんですよ~
BTS はおかしいものに対して、「おかしいでしょ」と意志を表しています
もちろん!ONF もです!!
おかしいものに対して、「おかしいでしょ」と意志を表している ARMY と FUSE は、私だけです
BTS や ONF が歌で表現していることを、言葉にして紹介している MC は、今現在、私だけだと思っています(たぶん…)
でもね…
集まれば、誰でも、MCになれるんです
つまり、名前がみつかるから、本当の ARMY になれます!!
個人が集まって塊になることで、MCの『声』が届きます
目を覚ました人々が集まったら、力になります
「愛するということ」を実際にできる人が、MC になれます!!
脱洗脳できた人が集まって、「新しい価値」を伝える MC になることが、私たちに「できること」なんですよ~
言い換えると…
脱洗脳できた兵士が集まって軍隊となり、「BTS のステレオの道を塞ぐ社会的偏見と抑圧」に向けて意志の弾丸を撃つことです
数は力です
単独行動の兵士ではなく、軍隊となって戦うことです
♬ 防弾と信じて~
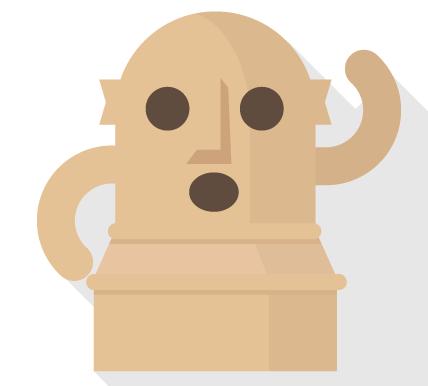
存在するのは、解釈です
だけど…
話の筋が通っている解釈は、使っている単語や方法が違っていても、ゴールは同じです
事必帰正!!
考え抜いてたどり着くのは、この方法です
真実の愛を表現できる、名前をみつけたファン
これが、本当の ARMY です!!
ルールは変えることができる
BTS も ONF も、「名前をみつけたファンと愛し合うことを求めている」というのを表現しています
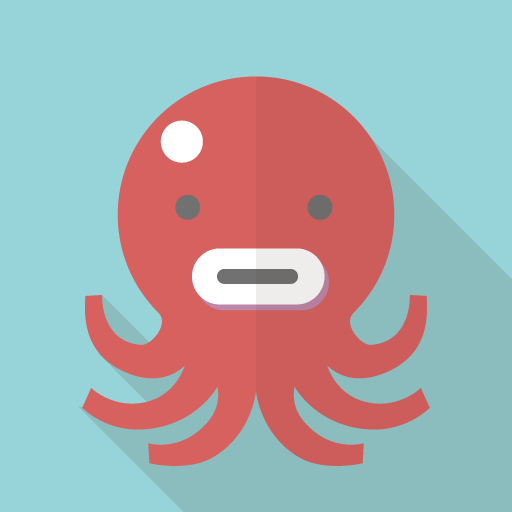
タコのお墨付き~!!
We need to change everything!
大事なのは、「ファンが知識を得ること」だったんですね~
最近、ようやく、気づきました!!
だから、このブログを読んでくださる方は、ステレオの道が見えてきたと思います!!
私たちが、モノラルの道に引きずり込まれるのをそのままにするか
はたまた
ステレオの道を塞いでいる社会的偏見と抑圧を、意志の弾丸で撃ち抜くか
どちらを選択しますか?
言い換えると…
アンドロイドとして生きるか
はたまた
人間として生きるか
どちらを選択しますか?
知は力なり!!
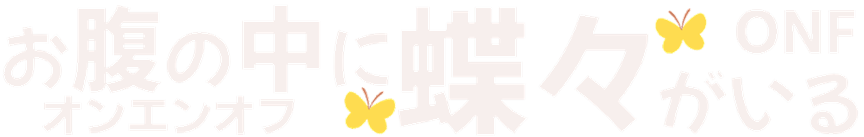






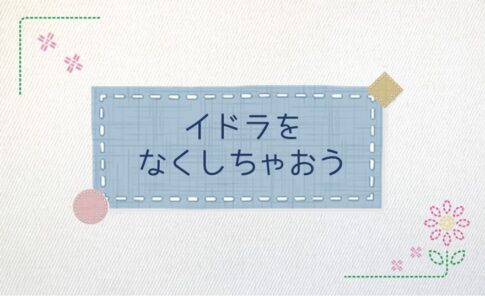
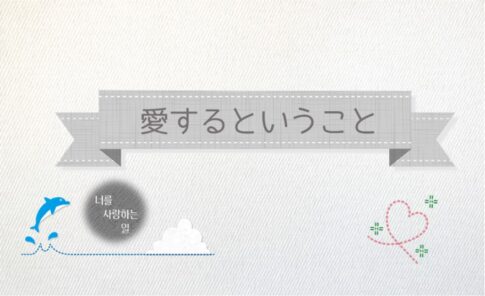

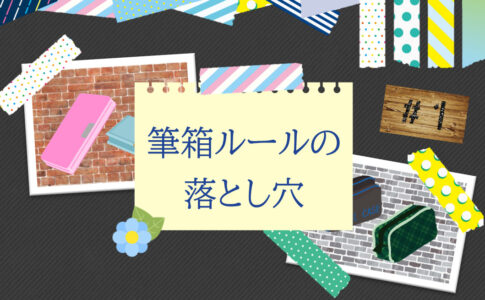
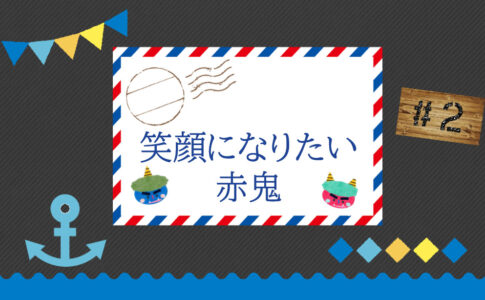




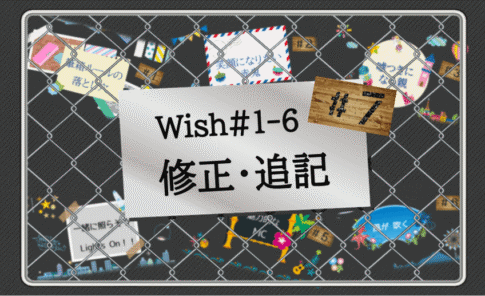



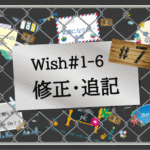
01 はじめに
02 新しい価値
03 知は力なり
04 現実にする